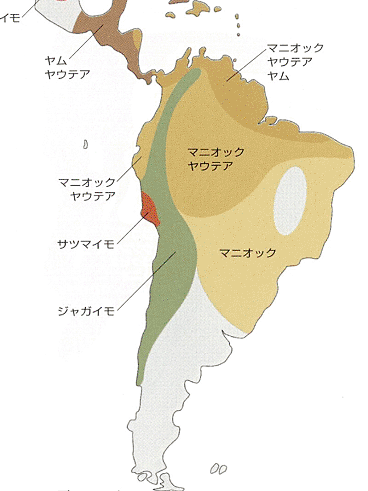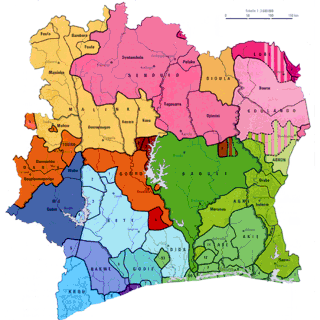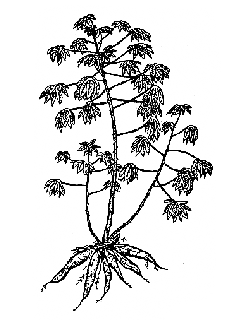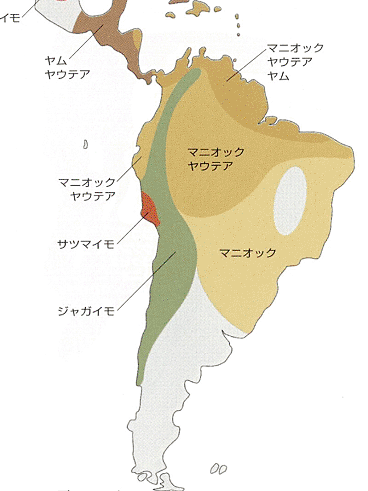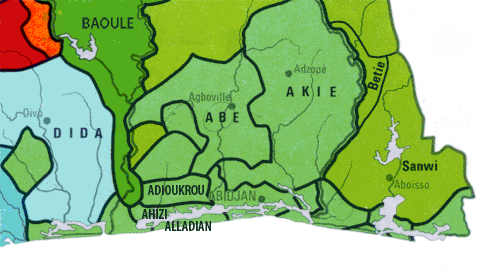コートジボワールの食文化――マニオクの加工食品・アチェケを中心に
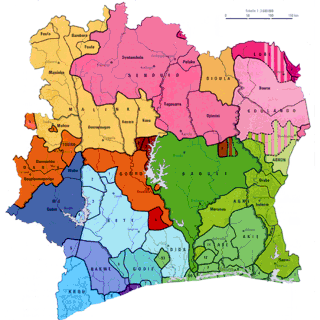
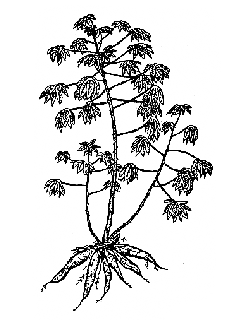
アチェケの加工には世界でも非常にまれな澱粉発酵過程が含まれる
コートジボワール東南部の食の特徴
- 具だくさんのスープ=「ソース」と主食の組み合わせが基本
- 主食のバラエティー
- マニオク:新しい作物。アチェケに加工。
- ヤムイモ:古くからの作物。ゆがく、餅にするなど。
- プランテン・バナナ(主食用の甘くないバナナ):焼く、揚げる(「アロコ」)、餅にする、捏ねる(「フフ」)
- タロイモ:アジュクルでは救荒作物。
- 米、パン (← 店で購入する)
- 豊富なパーム・オイル(未精製のオイルにはカロテンが豊富に含まれる)
マニオク manioc
- 学名:Manihot esculenta
- 原産:南米の熱帯雨林地帯
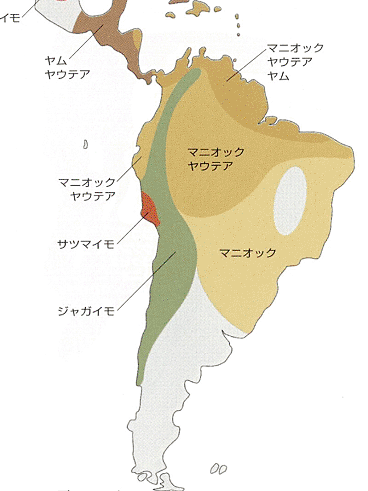
- 別名:「キャッサバ」「タピオカ」「イモの木」
- 導入:ギニア湾岸へは主に18世紀以降
- 特徴:品種により有毒のシアンが含まれる
- シアンを含む種類:「苦いマニオク」
- シアンを含まない種類:「甘いマニオク」
- 作物が伝わるのと同時に加工法(毒抜き方法)も伝わることが不可欠
マニオクの加工・調理法①
- 「苦い」マニオクは、まず芋をすりつぶすなどしてから澱粉をスターチにした後、あらためて調理を加えるのが、南米でもアフリカでも一般的である。
- 粉末にする処理工程で、水にさらしたり、熱処理したりする中で、シアンが抜ける。
- 毒性のない(弱い)「甘い」マニオクは、マニオクを中心的な主食作物とするところでは好まれない。救荒作物やおやつとして利用される。
マニオクの加工・調理法②
コートジボワールのアチェケ

- 分布:コートジボワール東南部
- 形状:クスクスに似ている
- 特徴
- 複雑で他に例のない加工法
- アジュクル人のアイデンティティ
- 日常食であるとともに儀礼食
- 加工の過程
- 前日 菌の準備

- 1日目-1 収穫

- 1日目-2 皮むき
- 1日目-3 洗浄 → 水浸

- 1日目-4 粉砕(同時に菌とパーム油を混入)

- 1日目-5 発酵(一晩)

- 2日目-1 プレスで水分除去

- 2日目-2 ほぐしと整形 "kok man"

- 2日目-3 半乾燥

- 2日目-4 選別(風選、篩(ふるい))

- 2日目-5 蒸し上げ

- 2日目-6 袋詰め → 完成

様々の道具
アチェケ専用具
- 篩:teme
- 木鉢:lofu
- 箕(大):waw
- 箕(小):ankok
- 蒸し器の枠:ahany
- へら:egb likgn
- しゃもじ:egb kpok
その他
- ナイフ:lab-li
- たらい:fanfan
- 大鍋 :ankpra
発酵について
- 澱粉を発酵させるのは希(例:パン)
- 黒カビ(ゆでたマニオクに繁殖させる)
- 各家庭が菌床を維持
- 発酵によるかすかな酸味
- 保存性:5日から1週間常温保存可能 ← 高温多湿な環境からすると驚くべきこと
- 古くなるほど乾燥が進むのも菌の働きか?
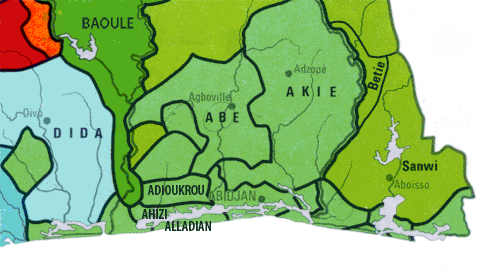
民族によって異なる語彙
歴史の浅い食品にもかかわらず民族ごとに名称は異なる
- バウレ BAOULE 語:"attiéké"
- アジュクル ADIOUKROU 語:"egb"
- アラディアン ALLADIAN 語:"akua"
- アイジ AHIZI 語:"fe"
- アキエ AKIE 語:"wu"
普及の拡大 (1990年代以降)
- 安価な加工済み主食食品として普及
- 1990年代から「ガルバ」と呼ばれるアチェケ専門の安食堂も増加
- 魚の唐揚げとアチェケのセットが「ガルバ」
- 輸出
- 製法の伝播
- アチェケ生産地域の拡大(工程の簡略化がみられる)
- ベナンでの「アチェケ=ガリ」と呼ばれるアチェケのイミテーションの発明